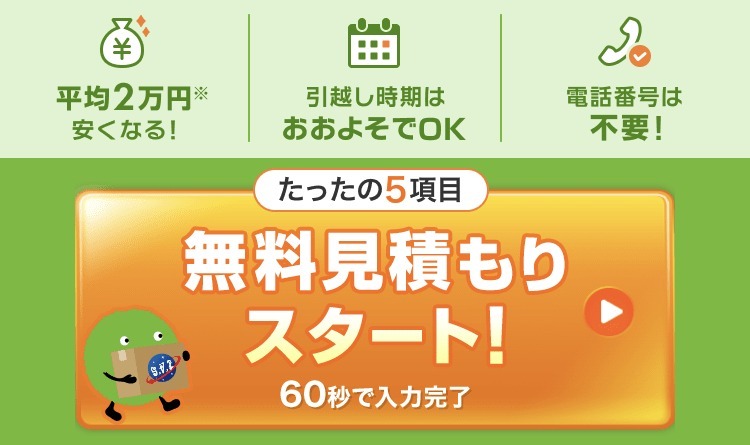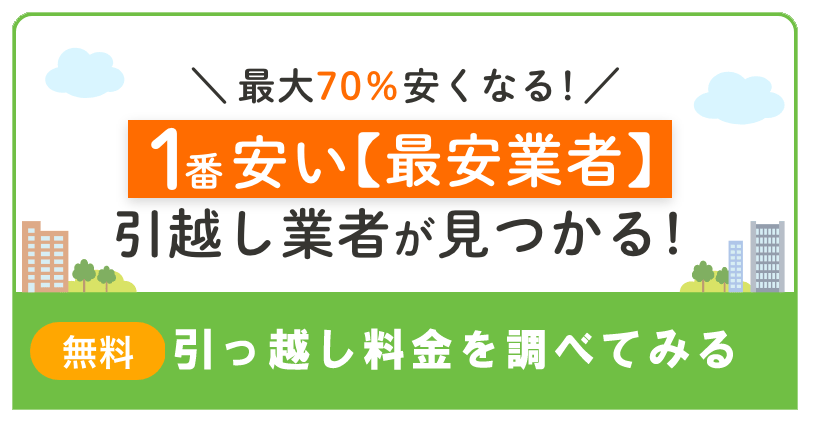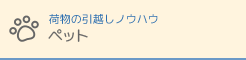- 引越し広場TOP
- 荷物の引越しノウハウ
- ペット
- ペットの運び方
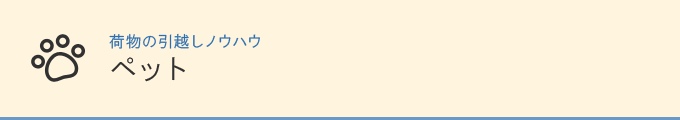
ペットの運び方
ペットを飼っている方は非常に多く、犬、猫、熱帯魚など様々ですが、引越しする際に知っておくと役立つ情報をまとめてみました。

- 運び方は大きく分けて3通り
- 犬や猫の場合
- 犬、猫以外の小動物の場合
- 熱帯魚などの魚類の場合
運び方は大きく分けて3通り
ペットと一緒に引越しをする場合の一般的な運搬方法は、大きく分けて3通りになります。
- 引越し主(飼い主)が一緒に連れて移動する方法
- 引越し業者に運搬を依頼する方法
- 直接、専門業者に依頼する方法
引越し主(飼い主)が一緒に連れて移動する方法
まず、引越し主(飼い主)が一緒に連れて移動する方法です。
いつも一緒に暮らしている飼い主やその家族と共に移動をする事は、ペットに大きな安心感を与えます。ペットの緊張を和らげるという意味で、非常に効果的です。自家用車で移動できるのであれば、ペットのストレスが少なくて済む可能性は高くなります。またコスト的にも、最もリーズナブルな方法と言えます。
鉄道をはじめとする交通機関を利用する場合には、緊張やストレスから暴れたり鳴いたりすることもあるので、周囲への対応や気配りが必要です。併せてそのペットの種類や大きさによっては、その交通機関を利用できないケースがありますので、事前に確認しておきましょう。
引越し業者に運搬を依頼する方法
次に、引越し業者に運搬を依頼する方法です。
少なくとも大手系の業者であれば、有料オプションにて運搬を請負うでしょう。その多くの場合は、業者が動物輸送の専門業者を手配し、その専門業者が運搬することになります。基本的には安心して任せられますが、一部の業者では自社トラックなどで運搬するケースもあります。
直接専門業者に依頼する方法
動物輸送の専門業者には、幅広い種類のペットに対応している業者や、一部種類に特化した業者などさまざまです。引越し業者を介さずに直接専門業者に依頼する場合、比較的コストを抑えることができるでしょう。
大切なペットを運ぶ業者は自分で選びたい、引越し業者にまかせるのが不安、少しでも引越し代を安くしたい、という人にはおすすめです。その分、業者探しや手配の手間はかかりますが、納得した上で業者に頼めれば安心してペットを預けることができるでしょう。
犬や猫の場合

犬や猫は賢い動物で、環境の変化に敏感に反応する性質を持っています。引越しの場合、周囲の状況の変化よって極度のストレスが生じて体調を崩したり、あるいはパニック状態に陥り暴れたり動き回ることがあります。
犬や猫の運搬には、できる限りストレスや不安を感じさせない対策が重要になります。
運搬前の対応
まず運搬前(荷物の搬出時)は、家の中を動き回ったり、逃げ出したりしないように注意します。犬の場合は必ず首輪をつけ、つきっきりで見ていてあげるようにしてください。
また猫の場合は、浴室などの狭くて人の出入りがない場所に一時的に閉じ込める形で隔離しておく方法が有効です。この時猫砂は捨てずにとっておきましょう。新居でトイレのしつけをする際に役立ちます。
運搬での対応
輸送では、飼い主自身が自動車や電車などに載せて運ぶ場合、必ずキャリーケース(ゲージ)に入れて運ぶようにします。ケースの中には日頃ペットが愛用している毛布・タオル類やおもちゃ類を入れておくと、ペットも幾分落ち着きます。
自動車で輸送する場合、マイカーであればペットがその環境に慣れている可能性がある他、ペットが鳴いたり暴れたりした時の対応もしやすく、犬や猫の運搬には一番向いている方法と言えるでしょう。
またペット専門のタクシー(ペットタクシー)の利用については、大抵の犬猫が乗車可能です。キャリーケースを使用しなくて良い点もメリットのひとつです。
キャリーケースに入れて電車で移動・運搬を行う場合、JR・私鉄共に「手回り品」扱いとなり、1個当たり280円で電車に乗せる事が可能です。ただしケースのサイズや重量に持込制限があります。
運搬後、新居での対応
無事新居に到着したら、できる限り一緒にいてあげるようにしましょう。犬の場合は、とにかく遊んで上げてください。
また、猫の場合は最初にトイレの場所を決めます。場所が決まったら取っておいた猫砂を入れたトイレを置き、猫の臭いがするものをたくさん置いてあげます。そのうち家の探索を始めると思いますので、そばでそっと見守りましょう。
犬・猫ともに、新居に慣れるまでに時間がかかります。引越し後2週間~1ヶ月程はできる限りそばにいてあげるようにしましょう。
犬・猫以外の小動物の場合

犬や猫以外の哺乳類の小動物や鳥類、爬虫類、昆虫などの引越しについては、基本的には、キャリーケース(ゲージ)などを使って、自分で運ぶ事ができます。
たとえばハムスター、リス、小鳥、カブトムシなどは、飼育に使用しているゲージ・ケースのまま、運ぶ事が可能です。普段生活している環境のまま移動することができるので、ペットたちへ負担が少なくて済みます。
また運ぶ際には、トラブル防止のためにケージ内の器具(回し車、給水器、エサ皿など)を取り外しておきます。そしてケースの上からダンボールや布などで覆ったり、バッグの中に入れたりして運びます。電車、バスなどの交通機関を利用する場合、犬や猫と同様サイズや重量に制限がありますので確認しましょう。
爬虫類については、布に包んだ上で箱・ケースなどに収納して運搬する事となります。公共の交通機関の利用については難しい場合が多いので、自分で運びたい場合は、基本的に自分の車で運ぶのが適切です。
周囲に迷惑を掛ける可能性がある場合は注意!!
犬や猫以外の小動物は自分で運ぶことも多いかと思いますが、大きさ、重さ、臭い、鳴き声などによっては、自分で運ぶ事が難しい場合があります。また、温度や湿度の管理に気を配らないといけない場合や、大量のペットを飼っている場合にも、自分だけでは運ぶのは難しいでしょう。
こういった場合、あまり無理をして運ぶとペット達にダメージを与えかねません。また、公共の交通機関を利用する場合、周囲に迷惑を掛ける可能性があります。
この問題は専門の輸送業者に依頼をすることで解決できます。引越し業者に相談するか、専門業者に直接依頼するか、安心してまかせられる運搬業者を選びましょう。
熱帯魚などの魚類の場合

魚類の運搬はいろいろと手間が掛かり、注意すべき点も多々あります。繊細な生き物を扱っている上に、水槽などの大きくて重量があり壊れやすいもの、加えて専用機器といったものも移動しなくてはなりません。
引越しをする際には、しっかり知識を身につけ、適切な方法で運搬しましょう。熱帯魚などの魚類に関しては、専門業者に運搬をまかせることを前提として考えてもよいかもしれません。
ここでは簡単に、熱帯魚などの魚類を安全に引越しするためのポイントをご紹介しています。
水槽に入れたまま運ぶ場合
まず住宅に設置されている水槽に入れたまま運ぶ場合、水槽の搬出・搬入にとても手間と時間が掛かります。そして車両輸送時の安全性の確保をしなくてはならず、そして水質・水温を適度に保つ事も必要となります。繊細な熱帯魚などの場合には、濾過装置などが必要となるかもしれません。
水槽から魚を取り出して運ぶ場合
水槽から魚を取り出して運ぶ場合は、水を入れたビニール袋に魚を移してから、ビニール袋を発泡スチロールなどの箱の中にいれます。振動によるトラブル防止のために水の量を工夫し、水漏れが無いよう防水に配慮が必要です。水槽の場合と同様、水温についても気を配らないといけない場合があります。
魚には、3~4日前からエサを与えないようにして、魚の糞尿の排泄を最小限に留めるようにします。これは、ビニール袋の中の水の水質をできるだけ綺麗に保ち、魚にアンモニア中毒などの悪影響を与えないためです。
 はじめての方へ
はじめての方へ